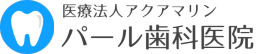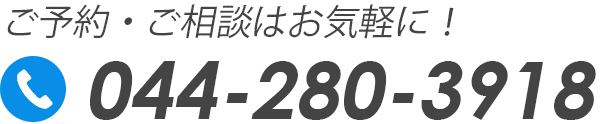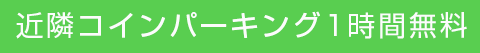歯列矯正の顎間ゴムとは?その効果や使い方、注意点を解説
みなさま、こんにちは
川崎市「小島新田」駅から徒歩1分のパール歯科医院です。
当院は、歯を守りたい、健康を実現したいと願う方の歯科医院で、担当歯科医師・歯科衛生士があなたの健康をサポートいたします。
目次
- はじめに
- 顎間ゴムの目的とは?
- 顎間ゴムの効果
- 顎間ゴムの使い方
- 使い始めの注意
- 顎間ゴム使用時の注意点
- 顎間ゴムを外す際のポイント
- まとめ
1.はじめに
今回は、顎間ゴムの目的や効果、使い方、注意点についてご紹介します
歯列矯正には、歯を整えるためのさまざまな道具や器具が使用されますが、その中でも「顎間ゴム(がっかんゴム)」は重要な役割を果たしています。顎間ゴムは歯や顎の位置を微調整するために用いられる小さなゴム製の輪で、上下の歯にかけることで、顎の動きや歯並びに影響を与えます。使い方や注意点についても知っておきましょう。

2.顎間ゴムの目的とは?
顎間ゴムは歯並びを良くするだけでなく、噛み合わせや顎の位置関係を調整するために使用されるものです。一般的な歯列矯正では、アライナーと呼ばれるマウスピースやブラケットとワイヤーを用いて歯を動かしていきますが、噛み合わせを整えたり上下の歯列の位置関係を正しくするためには、顎間ゴムはよく使用します。顎間ゴムを使うことで、次のような効果を期待することができます。

・噛み合わせ(咬合)の調整
上下の歯がしっかりと噛み合うように、歯列の位置関係を調整する。

・上下顎の位置の改善
顎の前後や左右の位置関係を整えることで、より自然で機能的な口元にする。
・歯の回転や傾きの補正
歯が正しい角度や位置に向かうために補助的に作用する。
3.顎間ゴムの効果
顎間ゴムの効果は、主に「上下の歯と顎の位置を微調整する」ことにあります。具体的には以下のような効果が期待されます。
・噛み合わせの安定化(咀嚼能率の向上)
噛み合わせが良いと食事の際にしっかりと食べ物を噛み砕くことができ、咀嚼能率が向上します。消化や栄養吸収もスムーズに進みます。また、顎や歯に過剰な負担がかからなくなり、長期的に健康な口腔環境を保つことができます。
・見た目の改善
顎間ゴムの使用で上下の顎の位置が調整されると、顔のバランスが整うことも多く、見た目にも良い影響を与えます。例えば、顎が引っ込み気味のケースでは前方に引き出され、逆に前に出過ぎている場合には後方に下がるように働きかけます。
・長期的な安定性の向上
矯正治療後も長く安定した歯並びを保つためには、噛み合わせの調整が欠かせません。顎間ゴムでしっかりと噛み合わせを整えておくことで後戻りのリスクが低くなり、治療効果が持続しやすくなります。
4.顎間ゴムの使い方
顎間ゴムの装着には慣れが必要です。初めての方は難しく感じることもあるかもしれませんが、使い方をしっかりと理解すれば簡単に装着できるようになります。
・装着の基本手順
①手を清潔にする
装着前に手を洗い、衛生面に注意しましょう。
②ゴムをかける位置を確認
歯科医師から指示された上下の歯にゴムをかけます。
③ゴムを準備する
小さなゴムは指にかけて、引っ張りやすくしておくとスムーズです。
④ゴムをかける
ゴムを指定された歯に引っ掛け、しっかりと装着します。初めのうちは鏡を見ながら行うとやりやすいでしょう。
5.使い始めの注意点
顎間ゴムは小さなゴムではありますが力が強いため、最初のうちは痛みを感じることがあります。しかし、数日経つと痛みが和らぐことがほとんどです。痛みが強い場合や違和感が続く場合には、無理をせず歯科医師に相談してください。
6.顎間ゴム使用時の注意点
顎間ゴムを使う際には、以下のポイントに注意しましょう。
・必ず毎日装着する
顎間ゴムは、1日の装着時間が短くなると効果が出にくくなります。歯科医師から指定された時間は必ず守りましょう。一般的には、食事と歯磨きのとき以外の時間は常に装着します。装着しない時間が数日つづいただけでも歯の位置は後戻りしてしまいます。
・汚れを防ぐためのケア
食事後は歯磨きをしっかり行い、清潔な状態でゴムを装着するように心がけましょう。衛生管理を怠ると、口臭やむし歯、歯周病の原因になることもあります。
・ゴムの交換
顎間ゴムは伸びやすい傾向にあります。1日に1回は新しいものに交換することおすすめします。長期間同じゴムを使い続けるとゴムの牽引力が低下するため効果が薄れ、矯正治療の進行に影響を及ぼす可能性があります。
・予備のゴムを持ち歩く
顎間ゴムを正しく使用していたとしても、ゴムが切れてしまうことがあります。外出する際には予備のゴムを持ち歩くようにしましょう。
7.顎間ゴムを外す際のポイント
顎間ゴムは指先を使って簡単に取り外しができますが、ゴムが小さいため失くしやすい点に注意しましょう。食事の際に取り外したら、ケースに入れるなどして保管しておくと紛失を防げます。
8.まとめ
歯列矯正における顎間ゴムの役割は、矯正治療をスムーズに進めていくうえで非常に重要なポイントとなります。しっかりとした噛み合わせと顎の位置関係を作り、矯正効果を安定させるために顎間ゴムの使用が必要です。装着のルールを守ることで、矯正治療の成功に一歩近づきます。顎間ゴムをうまく活用し、理想の歯並びと噛み合わせを手に入れましょう。当院ではワイヤー矯正をはじめインビザライン、小児矯正など各種矯正治療を行っております。ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください
当院の矯正治療について
https://www.pearl-dental-clinic.net/subject/orthodontics/
インビザライン(マウスピース矯正)について
https://www.pearl-dental-clinic.net/subject/invisalign/
パール歯科医院
日本口腔インプラント学会 認定インプラント専門医
院長 藤田陽一
院長紹介 https://www.pearl-dental-clinic.net/dr/
インプラント治療症例ブログ (後編)
川崎区にある歯医者 パール歯科医院 院長の藤田です。私は日本口腔インプラント学会 認定インプラント専門医を取得しております。当院ではインプラント治療・矯正治療など自費治療に力を入れています。
今回は当院のインプラント症例を2回に分けて、お話をさせて頂きます。
目次
- はじめに
- 症例紹介
- 治療計画
- インプラント埋入手術とサイナスリフト・ラテラルウィンドテクニック詳細
- 仮歯(TEK)にて咬合位の調整 ←今回はここから
- 最終補綴(セラミック冠)の装着
- まとめと考察
前回までの概要
両側奥歯が咬めなくなってしまった患者様のインプラント治療についてお話しさせていただきたいと思います。こちらの患者様ですが、左下奥歯と右上奥歯が欠損しており、かみ合う力が前歯に集中し前歯の動揺やかみ合わせの位置(咬合高径)の低下も見られていました。
インプラントを用いて審美性の獲得と正しいかみ合わせの回復をはかった症例
A case in which implants were used to achieve aesthetic results and restore correct occlusion
症例の概要
患者 60歳 女性
全身疾患等 無し 非喫煙者
主訴
前歯を綺麗にしたい
左上3本連結した歯が揺れている
奥歯でしっかり咬めるようにしたい
肩がこりやすい
歯ぎしりがひどい
前回からの続き
5.仮歯(TEK)にて咬合位の調整
左右奥歯にはインプラント上に仮歯が装着して、正しい咬合位(中心位)に誘導されています。
左上の挺出してしまった金属奥歯は、一度外して仮歯に置き換えています。左上ブリッジは患者様の十分な納得を得たうえで抜歯を行い。インプラントを3本埋め込みました。

左上前歯は審美上の問題も含め、インプラント埋入手術当日に仮歯(TEK)を装着しました。
多少外側に張り出していますが、これはセラミックの歯に置き換えた際し修正します。

その後左上前歯3本、インプラントの頭出し(2次オペ)を行いました。仮歯は、歯肉近くの形態をいくぶん形態修正して再装着しました。

6.最終補綴(セラミック冠)の装着
上顎の歯はすべてセラミックに置き換えました。下顎右奥歯もセラミックに置き換えました。
写真ではわかりずらいですが、かみ合わせの高さと位置も本来の正常な位置に回復させました。
この結果、肩こりや背中の張り歯ぎしりも緩和したとのことです。

最終補綴物(セラミックの歯)が入ってから、3年経過後のレントゲン写真です。患者様はしっかりメインテナンスに通ってくれているので、大きな問題はでていません。
7.まとめと考察
本症例では,主に仮歯を用いて咬合挙上を行い,歯冠修復処置により正しい前歯部被蓋関係の回復を行った。これによりいままで確認できなかった、前歯滑走誘導と側方運動時の犬歯誘導による臼歯部の離開を得ることができた。初診来院時では臼歯部の咬合支持が失われ垂直水平方向への咬合の不安定さが認められ、歯周組織も過大な咬合力も絡んだ上で、加速度的に咬合崩壊が進んでいる最中であった。このことにより顎関節ならび周囲筋肉の緊張は大きなものになり、就寝時の歯ぎしりや食いしばりを誘発し、歯の欠損が加速されるという状況であった。
臼歯部の欠損は、「後方歯がない」つまりブリッジにできない状態であり、必然的に部分入れ歯かインプラントになってしまう状況であった。部分入れ歯は、衛生面から考え就寝時は原則外すものである。そうなると就寝時の歯ぎしりによる、歯にかかるストレスは防ぎようがない。本症例は、インプラントを用いて就寝時に発生する過大な咬合力を受け止められるだけでなく、正常な咬合位置に戻すことに成功した。これにより歯ぎしり自体もなくなり副次的に発生していた肩や首の筋肉痛も消失していった。右上臼歯部のラテラルウィンドテクニックに注目が集まりやすいのであるが、それは枝葉の部分であり、本症例の着目は正常な咬合回復を前歯を含めた全顎で行ったことと考察する。
パール歯科医院では、患者様が安心してインプラント治療を受けられるよう、安全性に重きを置いて治療を行っています。これまでに多数の症例を扱ってきた実績もございますので、治療方法や費用についてのご相談はお気軽にお問合せ下さい。
パール歯科医院 インプラント治療7つのこだわりについて
https://www.pearl-dental-clinic.net/subject/implant2/
パール歯科医院 インプラント症例について
https://www.pearl-dental-clinic.net/case/
パール歯科医院
日本口腔インプラント学会 認定インプラント専門医
院長 藤田陽一
口臭と舌苔の関係について
みなさま、こんにちは
川崎市「小島新田」駅から徒歩1分のパール歯科医院です。
当院は、歯を守りたい、健康を実現したいと願う方の歯科医院で、担当歯科医師・歯科衛生士があなたの健康をサポートいたします。
目次
1.はじめに
2.口臭の主な原因
3.舌苔とは
4.舌苔と口臭の関係
5.舌苔による口臭の予防方法
6.舌苔が増える原因とは?
7.まとめ
- はじめに
今回は、口臭と舌苔の関係について紹介します。
皆さまは、舌苔(ぜったい)というものをご存知でしょうか?舌苔は舌の中央部にのっている細菌の集合体です。口臭は多くの人が経験する悩みのひとつで、社会的な影響や人間関係において大きなストレスをもたらすことがあります。口臭の原因はさまざまで食べ物や口腔内の健康状態に左右されますが、特に舌苔(ぜったい)との関係が深いとされています。口臭と舌苔の関係や、口臭予防のために舌苔をどのようにケアすべきかを知っておきましょう。
2.口臭の主な原因
口臭には多くの原因がありますが、口腔内で発生する口臭の大部分が口腔内の細菌によるものです。食べかすやプラークが歯や歯ぐきに溜まることでむし歯菌・歯周病菌が増殖し、揮発性硫黄化合物と呼ばれる臭いの元が発生します。さらには、歯周病やむし歯が口臭の原因になることもあります。他にも消化器系の問題や鼻の病気、糖尿病などが口臭の原因になることもありますが、口腔内の問題が最も多くの口臭原因を占めます。

3.舌苔とは?
舌苔とは、舌の表面に溜まる苔状の物質で灰白色をしめしますが、厚みが増すと黄白色に変わります。この舌苔は、食べかすや口腔内の細菌・白血球、口内の剥がれた細胞などが集まって形成されます。健康な舌には薄い舌苔が付着しているのが普通ですが、舌苔が増えすぎると口臭の原因になります。
また、味覚障害の原因になることもあります。

舌苔は、特に口腔内の乾燥や唾液の分泌不足が関係しています。口が乾燥すると舌の表面に付着した食べかすや細菌が流れにくくなり、舌苔が増加します。また、舌苔が厚くなると細菌が活発に繁殖し、臭いの元となる揮発性硫黄化合物を大量に発生させるため、口臭が強くなります。
4.舌苔と口臭の関係
舌苔が口臭に関与する理由は、その表面に細菌が大量に生息しているからです。舌の表面は舌乳頭という小さな突起が密集しており、これらの突起の間に細菌がたまりやすい構造になっています。特に嫌気性菌と呼ばれる細菌が舌苔の中で増殖し、食べかすや剥がれた細胞を分解することで、口臭の原因となる「揮発性硫黄化合物」が発生するのです。
特に揮発性硫黄化合物の中でも硫化水素やメチルメルカプタンといった成分は不快臭を発し、これがいわゆる口臭につながります。口腔内が乾燥しやすい人や口呼吸をしている人は特に舌苔が付きやすく、口臭のリスクが高まります。
5.舌苔による口臭の予防方法
舌苔を減らすことが、口臭を効果的に予防につながります。その方法について解説します。
・舌ブラシ
舌の表面に溜まった舌苔を取り除く専用の舌ブラシをご存知でしょうか?。舌専用のブラシで優しく舌の表面を磨くことで、舌苔を除去できます。ただし強く磨きすぎると舌の表面を傷つける恐れがあるため、軽い力で行うことがポイントです。1日1回は舌ブラシを使ったケアを取り入れるようにしましょう。


・水分補給をしっかり行う
口腔内の乾燥が舌苔付着の防止につながります。水分を十分に摂取することで、唾液の分泌が促進され、舌苔が付きにくくなります。特に食後や寝起き・長時間話をした後は口が乾燥しやすいため、水分補給を忘れないようにしましょう。
・バランスの取れた食生活
舌苔の原因となる口腔内の細菌を減らすためには免疫力の強化が重要です。栄養バランスの取れた食生活を心がけることも大切です。野菜や果物を多く摂取することで口腔内の健康が保たれ、舌苔の増加を防ぐことができます。
・適切な口腔ケア
舌苔だけでなく、歯と歯周病組織を清潔に保つことが口臭予防には欠かせません。歯磨きやデンタルフロス、洗口液を使って、食べかすやプラークをしっかりと取り除きましょう。特に、夜寝る前の口腔ケアが重要です。夜間は唾液の分泌が減少し口腔内の細菌が増えやすくなるため、寝る前にしっかりケアすることで口臭予防に繋がります。
・口呼吸を改善する
口呼吸は口腔内を乾燥させます。舌苔が増加する大きな原因となります。特に就寝時に口呼吸をしていると、朝起きたときに口臭が強くなることがあります。口呼吸の癖がある人は、鼻呼吸を意識することや、必要に応じて耳鼻科で相談するのも良いでしょう。
6.舌苔が増える原因とは?
舌苔が増える要因としては、上記のとおり口腔内の乾燥や唾液の分泌量の減少、口呼吸、栄養不足、ストレス、喫煙などが挙げられます。特に唾液の分泌が減少すると舌の表面に食べかすや細菌が残りやすくなり、舌苔が増えます。口腔内の環境が悪化する原因を減らすことが、舌苔を防ぐ鍵です。
7.まとめ
いかがでしたでしょうか。口臭と舌苔の関係について記しました。ききなれないと思いますが、舌苔は口臭の大きな原因となることが多く、そのケアを怠ると強い口臭を引き起こす可能性があります。日常的な舌のケアや、口腔内を清潔に保つ習慣を身につけることで、舌苔を防ぎ、口臭を予防しましょう。
定期検診やクリーニングのご予約も、お気軽に当院までお問合せください
お問合せ・ご予約はこちら
ご相談をご希望の方は、下記の電話番号までお電話いただき初診のご予約をいただくか、 下記の「無料相談メールフォーム」に相談内容をご記入の上、送信ボタンを押して下さい。 電話やメールではお答えするのが難しい場合には、初診のご予約をお願いする場合があります。 また、初診はすべて保険内での診察となります。
メールフォームでのご相談
ご予約前のご質問や疑問に
メールでお応えします
※電話での無料お悩み相談は承っておりません。
診療中にお受けしてしまうと、他の患者様にご迷惑をお掛けしてしまいますので、ご理解の程お願い申し上げます。